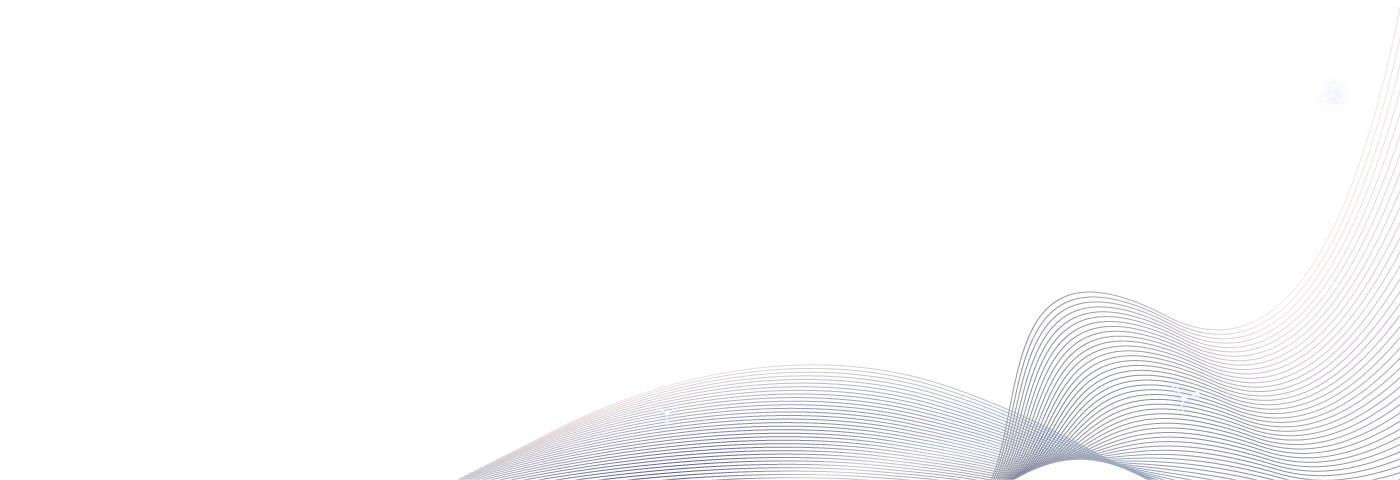
2025.2.27
生成AI(Generative AI)は、文章、画像、音声、動画などのコンテンツを自動生成する技術として、企業活動や個人利用で急速に普及しています。しかし、その一方で、著作権侵害、偽情報の拡散、プライバシー侵害といった法的問題や、情報漏洩、ブランド毀損、運用コストの増大など、企業が直面するリスクも顕在化しています。 こうした状況を受け、日本国内では法整備の必要性が叫ばれるようになり、企業側でも生成AI活用に伴うリスク対策が急務となっています。本記事では、国内法整備の今後の展望と課題、そして企業が取り組むべき具体的なリスク管理について解説します。
現時点で、日本国内には生成AIに特化した法律は存在しません。しかし、以下の既存法が間接的に関わってきます。
生成AIが収集・使用するデータが個人情報に該当する場合、個人情報保護法が適用されます。
例えば、SNS上の投稿を無断で学習データに使った場合、事前の同意が必要です。この点で、一部企業が個人情報保護法に抵触する可能性が指摘されています。
生成AIが学習に使用するデータや、生成されたコンテンツが著作物に類似する場合、著作権法が適用されます。
著作権侵害に該当するかどうかの基準が曖昧で、企業は知らないうちに法的リスクを抱えている場合があります。
競合他社のデータを無断で利用しAIモデルを学習させた場合、不正競争防止法が適用されるケースもあります。
日本政府は現在、欧州連合(EU)のAI規制法案「AI Act」など海外動向を参考に、生成AIに対する透明性確保やデータ利用適正化を目的とした新たな法整備を模索しています。特に以下の方向での進展が見込まれます。
今後、官民一体での検討会や試験事業を通じ、具体的な制度設計が進められる見通しです。
生成AIが既存の著作物を学習し、類似コンテンツを生成した場合、著作権侵害に該当する可能性があります。 対策としては、以下の例が挙げられます。
生成AIを活用する過程で、企業の機密情報が外部に漏洩する恐れがあります。 対策としては、以下の方法があります。
生成AIが不適切なコンテンツや偽情報を生成し、企業ブランドを毀損する可能性もあります。 対策として、以下のことが重要です。
生成AI導入後、想定以上にクラウド利用料が膨らむケースも報告されています。対策として、 以下のような管理が求められます
生成AIは、企業の業務効率化や新たな価値創出に大きく貢献する一方で、法的リスクや情報漏洩、ブランド毀損、コスト増大など、企業が直面する課題も数多く存在しています。 日本国内でも法整備が進む中、各企業は国際的な規制動向にも目を配りつつ、生成AI活用に向けたガバナンス強化とリスク管理体制の構築が不可欠です。また、政府による透明性確保義務化や高リスク分野での事前審査といった具体的な制度化が予測される中、企業もこうした流れを先取りし、準備を進めておく必要があります。
Colabofact株式会社では、生成AI活用に関する法的助言やリスク管理サポートを提供しております。導入に関するご相談は、ぜひお問い合わせください。